 |
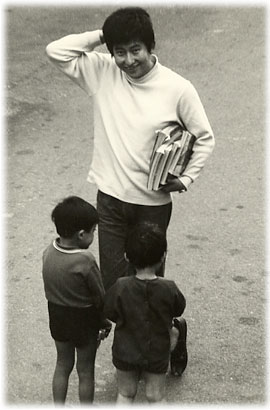
これはデビュー直後、雑誌の取材での1枚。
|
初挑戦のギャグマンガだったけれど、やってみたら、本当に速く描けた。アイディアにも特に困らないし、いったんキャラクターを作ってしまえば、それを転がすだけで、次々にギャグが出てくる。子供の頃から落語とかが好きでたくさん聴いていたし、コメディー映画もたくさん観ていたし、そういう素養も大きかったのだろう。「これはオレ、描けるな」。そう思って、さらにスピードを上げて描きまくった。ギャグマンガのページ数は、ストーリーマンガより短い。また、劇画やSF作品と違って、キャラクターや背景の絵も、ある程度シンプルな線で構わない。あっという間に、予定枚数の半分くらいのペン入れが終わった。
とは言っても、赤塚不二夫先生に代表されるような、既存のギャグマンガを描くつもりはなかった。いずれはストーリーマンガを描くつもりだったから、ストーリー性のあるギャグ、いわば“ストーリーギャグ”ともいうべきものを目指したのだ。思いついたきっかけは、ジャンポール・ベルモンドの『リオの男』という無声映画を観たことだった。恋人をさらわれた主人公が、パリの街角からブラジルの奥地まで追いかけて助けるという、ただそれだけの話だ。主人公は寡黙な男でほとんど喋らないが、体を張って必死に難関を突破していく姿が、ものすごく可笑しかった。こういうジャンルをスラップスティックということは、あとで知った。
この『リオの男』を観たことで、別に口で可笑しいことを言わなくても、ギャグマンガは作れるんだということがわかった。ストーリーがしっかりあっても、主人公の動きで笑わせることができる。このストーリーギャグなら、自分のストーリーマンガの演出や、石森先生の下で覚えた演出技法も、みんな活かせるなと思った。
しかし、そういうテイストの作品を目指したおかげで、仕上げにはかなりの時間が必要になった。作品の中にはちゃんと背景を入れたかったし、列車の爆発など派手な場面も使いたかった。それで、ある程度完成のめどが立ったところで、石森先生に「持ち込みに行きたいんですが、少し時間をもらえませんか」と相談した。その頃には後輩のアシスタントたちを、かなり描ける状態にまで仕込んでおいたし、少々余裕のある時期を見計らって切り出したから、先生も快く3ヵ月の休みをくれた。描きさえすればデビューできると思っていたので、ああこれでやっとデビューできると嬉しかった。僕は3ヵ月で作品を完成させ、いよいよ出版社に持ち込みを再開した。
だが「ギャグなんだかストーリーなんだか、よくわかんないね」というのが、最初に持っていった『少年サンデー』の編集者の感想だった。「そこが面白いんじゃないですか」と食い下がったが、その人には全く理解してもらえなかった。僕は、作品を抱えて編集部を出るしかなかった。ただ、そのときに言われた「台詞がつまんない」という言葉は、耳に残っていた。確かに、ストーリー性を意識して、真面目な台詞ばっかりだったかもしれないと思った。そこで家に帰ると、登場人物の台詞を全部書き直した。こいつは関西弁にしてみようとか、工夫をこらしたのだ。特に、ヒゲだらけの男を「オホホ、ウフフ」と女性の喋り方にしたら、すごく気持ち悪くなり、これは面白いかもしれないぞと思った。この人物は、『ハレンチ学園』のヒゲゴジラの原型となった。
そして、描き直した作品を『ぼくら』編集部に持ち込むことにした。そこに大きなチャンスが転がっていることを、当然ながら、僕はまだ知らなかった。
<第15回/おわり>
(c)永井豪/ダイナミックプロダクション2002
(c)Go Nagai/Dynamic Production Co., Ltd. 2002
|




