

 
|
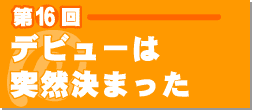
|
原稿を預けてから半年くらいたったとき、突然Tさんから呼び出しの電話があった。編集部へ行くと「アレ、もしかしたら使うかもしれないから」と言う。当時『ぼくら』で連載していた、園田光慶さんの原稿が落ちそうだというのだ。「そうですか、是非使ってください」と、僕はまた期待を膨らませたが、結局園田さんの原稿は間に合ってしまった。また空振りである。 |
|
全面的に台詞を書き直したギャグ作品は、『007シリーズ』のパロディーのようなスパイ物だった。僕はそれに『それいけスイート』というタイトルを付けて、当時の少年月刊誌『ぼくら』に持っていった。浪人時代の持ち込みとは違って、この頃は持ち込み先も、ある程度選択することができた。石森先生のところでチーフ・アシスタントをやっていたため、出版社の人と話をする機会が多かったからだ。僕は、自分の作品をわかってくれそうな編集者、気の合いそうな編集者を選んで、作品を持ち込んだ。 『ぼくら』にはTさんという編集者がいて、僕はこの人を訪ねていった。一読すると、「じゃあ、預かるわ」と言うので、僕は原稿を置いて家に帰った。初めて作品を受け取ってもらえたし、面白さには自信があったので、そのうちどこかで使ってもらえるだろうと、僕はかなり期待した。しかし、Tさんからは連絡が全然来なかった。そのうち石森先生にもらった休みも終わり、またアシスタント生活に戻ることになった。正直な話、かなり落胆した。次はいつ描けるのだろうと考えると、気が重かった。 原稿を預けてから半年くらいたったとき、突然Tさんから呼び出しの電話があった。編集部へ行くと「アレ、もしかしたら使うかもしれないから」と言う。当時『ぼくら』で連載していた、園田光慶さんの原稿が落ちそうだというのだ。「そうですか、是非使ってください」と、僕はまた期待を膨らませたが、結局園田さんの原稿は間に合ってしまった。また空振りである。あとでわかったのだが、Tさんは忙しさに紛れて、僕の原稿をロッカーに入れっぱなしにしていたらしい。それで、園田さんの代わりの原稿ないか、という騒ぎになったとき、ふと思い出して引っぱり出したようだ。 しかし、これが逆転デビューにつながった。園田さんの原稿の代わりに雑誌に載せる可能性があったため、編集長が僕の作品を初めて読んだ。そして、「これ、面白いじゃないか」と気に入ってくれたのだ。そのとき『ぼくら』編集部では、あるTVアニメの原作を使って、同時にマンガを連載しようという企画があって、編集長は、そのマンガ版のほうを僕に描かせてはどうか、と言い出したのだ。僕の絵柄がアニメにピッタリだと感じたらしく、また、アニメが原作だから大先生には頼みにくいので、新人を起用したいという考えもあったようだ。これが、僕の最初の連載となる『ちびっこ怪獣ヤダモン』だった。一気に連載が決まるとは思ってなかったので、さすがに僕も驚いたが、もちろん断る理由はない。Sさんという編集者が、正式に担当としてついた。こうして僕は、めでたくマンガ家になったのだ。 |
さすがに編集長も、持ち込みからいきなり連載というのはどうかと考えたらしく、練習の意味もあって、『ヤダモン』の前に1回読み切りを描くことになった。それがデビュー作『目明しポリ吉』である。このデビュー作には、今もってわからない謎がある。僕はこの読み切り作品に、『目明しポリ助』というタイトルを付けたはずなのだが、なぜか掲載時には『ポリ吉』になっていたのだ。現代的なギャグを盛り込んだ岡っ引きのマンガなので、主人公の名前を「ポリス」を和風にして「ポリ助」と付けた。だから、僕の記憶違いではない。おそらく、担当編集者のSさんが変えたのだと思うが、当時はなかなか聞けなかった。その後Sさんは名編集者となり、最近惜しくも亡くなってしまった。だからタイトルが変わった経緯は、今も謎のままだ。
ところで、最初に『ぼくら』に持ち込んだ『それいけスイート』は、園田さんの原稿が落ちていれば掲載されるはずだったから、いわば幻のデビュー作ということになる。だがその後、なぜか発表する機会がなかった。その原稿がどうなったかと言うと、現在は友人でSF作家の高千穂遙氏が所蔵している。高千穂氏は、僕のファンクラブを作ってくれた人で、僕はそのお礼として『スイート』の原稿をあげてしまったらしいのだ。自分であげていながら、僕はそのことをすっかり忘れていた。あとで「返せ」と言ったのだが、高千穂氏は「もうオレのもんだ、今に値が付く」と言って返してくれない。マンガ家30周年を迎えたとき、その記念出版物で掲載させてくれと頼んだが、今度は書庫の奥にしまいこんでいるので出てこないという。仕方ないので、ファンクラブの人が持っていたコピーを借りて収録した。自分の作品なのに、困ったものだ。 というわけで、園田光慶さんが原稿を落っことしそうになったお陰で、僕は偶然デビューできたとも言える。お礼を言うのもヘンだが、いずれ園田さんにはご挨拶はしたいと思っていたところ、意外に早くその機会は来た。園田さんが、また原稿を落っことしそうになったのだ。僕は二晩ほどお手伝いに行って、「お礼」をすることができた。 たまたま原稿を預けていたときに、そういうチャンスが訪れたわけで、デビューに関しては運がよかったと言うべきだろう。何しろ新人がデビューするのは、本当に難しい時代だったのだ。もし原稿を預けていなかったら、もし園田さんが原稿を落としそうにならなかったら──。そのときは、僕はまた石森先生のアシスタントに逆戻りして、休みをもらっては原稿を描き貯めて持ち込みに行く生活を、何度も何度も繰り返していたかもしれない。 <第16回/おわり>
(c)永井豪/ダイナミックプロダクション2002 (c)Go Nagai/Dynamic Production Co., Ltd. 2002 |
|
|
|