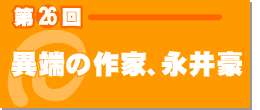|
話を元に戻そう。『魔王ダンテ』を描いたことで、僕のストーリーマンガ家としての才能が認められたかというと、そんなことは全然なかった。むしろ、ますます「ヘンなものを描く、ヘンな才能のマンガ家」という評価が固まったようだった。一方で僕も、マンガ雑誌の編集部に対して不満を持っていた。これは面白いぞと自信を持って出した企画でも、その面白さをちっともわかってくれない。連載の途中でも、担当編集者があれこれ見当違いのことを言ってきて、「わかってないなあ……」と疲れることも多かった。
たとえば『あばしり一家』を描いたときがそうだ。『あばしり一家』を描くとき、僕は最初から女の子を主人公にしたいと考えていた。でも、話しても話しても、編集部は許してくれなかった。少年誌で女の子が主人公の作品は、過去にいろんな人が失敗しているから、というのが理由だった。「手塚治虫先生も、横山光輝先生も、みんな失敗したんだぞ」と言うので、「いや、僕は別人ですから」と反論すると、しまいには「女の子を主人公にしたら、絶対に売れない。これは少年マンガの常識です!」とまで言われた。
もうこれは説得するのは無理だ、と判断した僕は、「わかりました。悪人一家の話でいきます」と折れて見せた。「ああ、それはいいね」ということで連載がスタートすると、1回目からいきなり、菊の助という女の子を主人公にして、他の登場人物は全部脇役にしていった。1回目から人気が取れたので、そのまま何も言われずに済み、『あばしり一家』は単行本15巻という長編連載になった。僕はその後も『キューティーハニー』や『けっこう仮面』など、女の子が主人公の作品をいくつもヒットさせた。今やそんなものは当たり前で、特にオタク系の作品では、女の子が主人公のマンガばかりだ。だから僕は、ひそかに「この分野を切り拓いたのはオレだ」と思っていたりする。
こうして僕は、「どうせわかってもらえないのなら、編集の人は上手くだまして、自分の描きたいことを描こう」と考えるようになった。打ち合わせのときには「はい、わかりました。じゃあそういうことで」と言って、全然違うことを描いたりした。さらに、描いた後で描き直しを求められたりしないように、わざと締め切りギリギリに原稿を渡したりした。そしてついに、「永井豪は、好きに描かせておくしかない」と言われるようになった。
あらゆる雑誌で連載を持って、どれも結構な人気を取りつつも、僕はマンガ業界では「異端の作家」だったのだ。不思議な作品を描きたがり、話を聞いただけでは面白いのかどうかわからない。しかし、描いたものは何故か子供にはウケるから、雑誌としては僕の作品は欲しい──。マンガ雑誌編集部の僕に対する評価は、こんな感じではなかったろうか。要するに僕は、登場した時代が早すぎたのだろう。子供や下の世代には、熱狂的に指示された。でも、同世代や年上の人には、なかなか理解してもらえなかった。
そういうわけで、新しいストーリーものの依頼は、どのマンガ雑誌からも来なかった。でも僕は、実は『魔王ダンテ』の連載中から、次のストーリーものの企画をこっそり進めていた。そう、マンガ業界とは違うところから、ある新しい企画を持ち込まれていたのだ。
<第26回/おわり>
(c)永井豪/ダイナミックプロダクション2002-2003
(c)Go Nagai/Dynamic Production Co., Ltd. 2002-2003
|