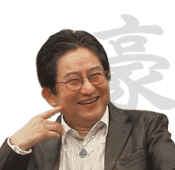




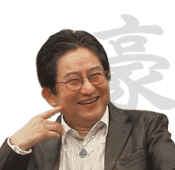 |
 |
 |
 | 『ハレンチ学園』で全国のPTAを敵に回し、『デビルマン』で宗教世界を転覆させ、『マジンガーZ』で巨大ロボットアニメを生み出し、『キューティーハニー』でおたく文化の教祖に。デビュー以来35年、常にマンガ界に革命を起こし続けてきた巨人・永井豪とは何か? 創作のヒミツと七転八倒のマンガ家人生が、いま初めて明らかになる! |
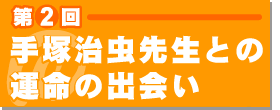 | 車や海を怖がった話もそうだけど、僕はちょっとエキセントリックな子供だった。空想癖があったし、幽霊を見たりということもあった。だから、よその家の子供たちと外で遊ぶよりは、兄弟と家の中で遊んでいるのが好きだった。そういう中で、僕の運命を決定づける出来事があった。 |
 | 東京での授業はどれもこれも、僕には英語の授業のように思えた。東京のほうが、輪島よりはるかに内容が進んでいて、さっぱり授業についていけなかったのだ。教科書も、輪島のものとは全然違っていた。試験があると、いつも真ん中より上にいったことがなかった。だから僕は、小学校の3年生くらいまで、自分は劣等生なんだと思っていた。 |
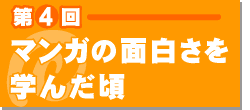 | 中学生になったら、今度はクラスに貸本マンガに詳しいヤツがいた。そいつは「白土三平ってすごいんだよ」と、読んでみるように僕に勧めた。読んでみたら、確かにすごかった。マンガの中で血がばんばん飛んでいる。当時はマンガの中で、血なんか描いちゃいけない風潮だったのに。そして白土三平先生のマンガを見ていたら、突然、幼い頃に体験した衝撃的な記憶が甦ってきた。 |
 | その頃の『キネマ旬報』には、必ず1本、映画のシナリオが載っていた。僕はそのシ ナリオをむさぼるように読み、添えられている写真の、ほんの1〜2枚だけを頼りに、 映画の場面をあれこれ想像して楽しんでいた。今思えばそれが、イメージするという マンガ家に必要な行為にとって、どれだけ勉強になったか。 |
 |
 |
 |
 | 『デビルマンレディー』という作品がある。この“レディー”のキャラクター造形は、実は連載を始める何年も前に、いたずら描きをしていて出来たものなのだ。それでのちに新連載を始めようというとき、編集長にいくつか出したアイディアがどれも受け付けてもらえなくて、ついに思い余って、ほったらかしにしてあったレディーのいたずら描きを見せた。そうしたら、「あっ!これだよ!」と言われて、そのまま新連載作品となったという訳だ。 |
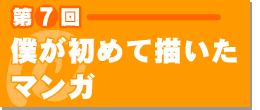 | 僕は小学生のときにはもう、漠然とではあっても、マンガ家になるんだと決めていた。でも、実際に描き始めたのは高校生になってからだ。なぜそれまで描かなくて、なぜ高校生になってから描き始めたのだろうか。考えてみたのだが、たぶん画力の問題ではなくて、この頃になってようやく、ストーリーを作る力がついたからではないだろうか。 |
 | 作品を描いても描いても、描き足りたという気がしない。1本描くたびに、自分はこれで、どのくらいの人間の記憶にとどまっていられるだろうかと思うし、自分が生きていたという証拠は、本当に世の中に残っているんだろうか、という不安も消えない。だから、『ハレンチ学園』を描いたときに日本中からボロクソに叩かれたけれど、そんなの屁でもなかった。 |
 | 僕は再び編集部を訪れて、どかっと原稿の束を出した。長い時間かかって目を通した編集者の返事は、こうだった。「面白いんだけどね、こんな長い話、新人じゃ載せられないよ」。面白いといいながら、短編でもダメ、長編でもダメ。僕は我慢できずに、ついに切り出した。「要するに、雑誌では新人は使わないんですね?」。 |
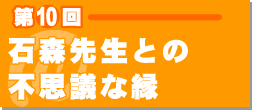 | 「今ピンチなんだ!」。石森先生だった。原稿が雑誌の締め切りに間に合わないので、アシスタントとして手伝いに来てくれというのだ。1回見てもらっただけだったのだが、石森先生は僕の絵を覚えていたらしい。いきなりプロのマンガの背景を描くのか、と緊張したけれど、真剣に僕の作品を見てくれた石森先生の頼みだし、急いで先生の仕事場に駆けつけた。 |
 | この頃は、本当にきつかった。例えば、13社の編集者が、仕事場にずらっと並んだことがあった。もちろん、みんな落ちそうな原稿を待っているのだ。どこかのを先に上げると大変なことになるから、石森先生は13社の原稿を全部並べて、ものすごいスピードで描いていく。描き終わると、僕らの前の畳にどんどん置いていく。僕らが1枚の背景を描き終えると、ひったくるようにその担当編集者が持っていく。 |
 | 家には全く帰れない。風呂にも入れないし、食事の時間さえほとんど取れない。体重も減って、ガリガリに痩せこけた。あるとき、とにかく目を覚まそうと、水で顔を洗い、ふと鏡を見ると、僕の顔は鬼のようなものすごい形相になっていた。目が落ちくぼんで、そのくせヘンにギラギラ、ギョロギョロしている。これがオレの顔かあ、と呆然と眺めるしかなかった。この頃の仕事場は、まさに地獄のようだった。 |
 | 石森先生は、どうしてあんなに速く絵が描けるのか。どうしてあんなに速く手が動くのか。もちろん運動神経もいいのだが、秘密の一つは、ペンの持ち方にあった。石森先生は、極端にペンを寝かせて持っていたのだ。真似してやってみると、ペンがすごく柔らかく使える。墨をたっぽんと付けて、サラサラサラとものすごく速く描ける。 |
 | 前に石森先生の原稿を描く速さについて書いたが、大量の作品が描けたのは、単に手が速く動くというだけじゃなくて、もう一つテクニックがあった。それは、「ページをゴマカす」テクニックだ。ページをゴマカすといっても、落語の『時そば』みたいに、少ない枚数の原稿を渡すわけじゃない。ごく少ない時間で枚数を稼ぐ“技”を、編み出しては使っていたのだ。 |
 | 初挑戦のギャグマンガだったけれど、やってみたら、本当に速く描けた。アイディアにも特に困らないし、いったんキャラクターを作ってしまえば、それを転がすだけで、次々にギャグが出てくる。子供の頃から落語とかが好きでたくさん聴いていたし、コメディー映画もたくさん観ていたし、そういう素養も大きかったのだろう。 |
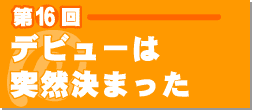 | 原稿を預けてから半年くらいたったとき、突然Tさんから呼び出しの電話があった。編集部へ行くと「アレ、もしかしたら使うかもしれないから」と言う。当時『ぼくら』で連載していた、園田光慶さんの原稿が落ちそうだというのだ。「そうですか、是非使ってください」と、僕はまた期待を膨らませたが、結局園田さんの原稿は間に合ってしまった。また空振りである。 |
 | でも一方で、僕はそんなマンガ家という職業に不安を抱き始めていた。デビュー当時、僕の原稿料は1p1200円だったが、これは月に20〜30枚描けば、サラリーマンの月給くらいにはなるかな、という金額だった。だから、楽々食っていけると思ったのだが、仕事が増えてきて、連載が次々と決まり、アシスタントを一人二人と雇い始めると、アシスタントの給料で、たちまち赤字になってしまった。 |

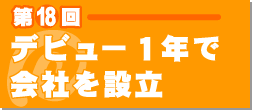 | マンガ家は、お金の交渉は苦手だ。あんまり粘ると仕事がもらえなくなるんじゃないかという不安もあって、言いたいこともなかなか言えない。特に新人である僕が、百戦錬磨の編集者と渡り合うのは大変だった。今、プロ野球界でも、年俸や条件の交渉のために、代理人制度を導入しようという動きがあるが、僕はもう35年以上前に、同じ問題に突き当たっていた。 |
 | この頃僕は、『別冊少年マガジン』を中心に『剣マン』シリーズを描いていたが、ここでも内容に対する不可解な反応にでくわした。作品の中で僕は、ビキニの水着の女の子を描いた。そうしたら原稿を受け取った編集者が、「水着はちょっとね……特に、ビキニはマズイよ」と言うのだ。僕はビックリしてその理由を聞くと、「だって少年マンガだから」と言うではないか。 |
 | 『ハレンチ学園』は、最初はそんなにエッチなマンガでもなかったのだが、ある時、ちょっとエッチな内容だった回に、読者が編集部に文句を言ってきたことがあった。「ハハーン、狙い目はココだな」と思った僕は、さらにエッチ度をエスカレートさせた。読者は大喜びで、人気はどんどん急上昇。そしてその一方で、ふと気がつくと、いつの間にか抗議の声がかなり大きくなっていた。 |
 | 教師やPTAといった、大人からの攻撃が激しくなるのと逆に、読者である子供の読者からのファンレターは、どんどん増える一方だった。「もっとやってください!」「大人はズルイ! がんばれ!」というものや、中には「大人は自分でエッチなことしているのを、僕らは知っているぞ!」というものもあった。この山のように来るファンレターが、僕にとって何よりの励みとなった。 |
 | 今や毎日のように、教師たちの不祥事が新聞を賑わせている。特に、女子生徒に対するセクハラ事件が多い。その次に多いのが、生徒に暴力を振るったというニュースだ。でも、こういう事件が昔はなかったかというと、そんなことはない。実はこういうことは昔からあって、表沙汰にならなかっただけなのだ。 |
 | 今だったら、過労死するマンガ家が出てもおかしくない。でもこの当時の人は、不思議と死ななかった。そしてみんな、「ついてこられないヤツは、マンガ家を辞めればいい」と思っていた。特に僕は、石森先生の影響を受けていたので、マンガ家とはそういうものだと思っていたし、これくらい仕事をやっていないと、マンガ界では生き残れないと思っていた。 |
 | きっと、自分のギャグに自分が飽きるときが必ず来る。そうなったら描いていくのはものすごく辛い。それに、一人の人間のギャグに、そんなにパターンがあるわけじゃない。読者はだんだんそれに慣れ、やがて飽きてくる。過去のマンガ家を見ても、一時期はすごくても、長続きした人はいない。赤塚不二夫先生ですら、大活躍した期間は意外に短いのだ。 |
 | 当時『少年マガジン』の編集長だったUさんが、『ぼくらマガジン』の編集長を兼任することになった。そして、「君を柱にしていくから、何でもいいからとにかく描け」と言う。他誌で連載を何本も抱え、とてもこれ以上描けないと思っていたのだが、この「何でもいいから」という言葉に、ぴくりときた。「ストーリーマンガでも、いいですか?」「いいよ」。僕は、思わず連載を引き受けてしまった。 |
 | あらゆる雑誌で連載を持って、どれも結構な人気を取りつつも、僕はマンガ業界では「異端の作家」だったのだ。不思議な作品を描きたがり、話を聞いただけでは面白いのかどうかわからない。しかし、描いたものは何故か子供にはウケるから、雑誌としては僕の作品は欲しい──。マンガ雑誌編集部の僕に対する評価は、こんな感じではなかったろうか。要するに僕は、登場した時代が早すぎたのだろう。 |
 | 僕が描いた主人公であるデビルマンの絵、それに敵の悪魔たちの絵を、アニメ会社の人がTV局の人に見せた時こう言われたそうだ。「面白い企画ですけれど、主人公はどこにいるんですか?」。アニメ会社の人はデビルマンを指して「これですよ」と答えた。「えっ、これは敵のボスじゃないんですか?」と更に答えが返ってきたそうだ。あまりの不気味な姿にデビルマンが主人公だとは誰もわからなかったらしい。 |
 | おかしいな、と思い始めたのは、連載も終盤にさしかかってからだった。どうも、物語をリードしているのは、主人公の不動明ではなく、飛鳥了のような気がしてきたのだ。場面によっては、どっちが主役かわからないような感さえある。よく考えると、飛鳥了にはいろいろ不思議なことがあった。 |
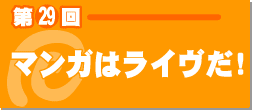 | キャラクターが思いもかけない変貌を遂げる一番の理由は、僕が「ストーリーを最後まで決めない」からだ。まず、そうしたほうが絶対面白い作品になる。次に、そうしたほうが描いていて自分が面白い。また、デビュー以来ずっと締め切りに追われていたので、ストーリーを最後まで考えて、それからネームをやるような時間の余裕がない。だから、ネームを紙に起こしながら、ストーリーを作っていく。 |
 | 『デビルマンレディー』の連載中も、そうだった。読者に「レディーは美樹ちゃんでしょう」と予想されてしまうと、「絶対そうするもんか!」と思ってしまう。それでもあんまりそう言われるので、“美樹ちゃん=レディー論争”に引導を渡すために、不動ジュンの弟のガールフレンド、というチョイ役で登場させた。 |
 |
 |
 |
 | そのとき僕は、喫茶店で連載中の作品のネームをやろうと、ノートを抱えて道端で信号待ちをしていた。道路は渋滞していて、車はなかなか進まない。僕は、「こういうとき車が立ち上がって、前の車をまたいでいけたらいいだろうなあ」と思った。車がのっしのっしと、他の車をまたいで歩くイメージが頭に浮かんだ。その瞬間、アイディアがひらめいた。 |
 | 『鉄人』『ロボ』は「遠隔操縦型」、『アトム』は「人工知能型」で、『マジンガー』は「搭乗型」のロボットだというわけだ。もちろん僕自身、かつてないロボットを生み出そうとしたのだから、違うのは当然だ。でも最近になって、僕が『マジンガーZ』のような「搭乗型」ロボットを描いた理由は、既にあったロボット像を避けた、というだけではないような気がしている。 |
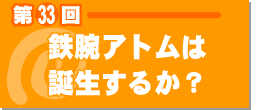 | だが、僕は思うのだ。完全な人間型ロボットができて、完全な人工知能が開発されても、「アトム」はできないだろう、と。人間と同じように考える人工知能が発明されて、人間と同じように動けるロボットに組み込まれたとしよう。そのとき、それはアトムのような“いい子”になるだろうか。 |
 | 『マジンガーZ』の造形は、中世の鎧から発想したと書いたけれど、子供の頃には、その他にもいろんなデザインのロボットを、ノートにイタズラ描きしていた。そしてそれをもとに、粘土で立体のロボットを作って、弟と一緒に遊んでいたのだ。ジオラマみたいな舞台を作って、何体も作った粘土のロボットを、どれが一番強いかと考えて強そうな順に並べたり、突然自分が神になって壊したり。 |
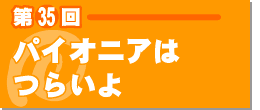 | 仕事でヨーロッパに行った時、あちらのメディアから取材を受け、こんな事を聞かれた。「どうしてあなたは、ディズニーランドみたいな遊園地を造らないのですか?」。なぜ造れるだけのお金があるのに造らないんだ、というニュアンスだったと記憶しているが、ヨーロッパで僕の作品が、驚異的なヒットを飛ばしていたがために、出た質問だった。 |
 | 3歳のときの恐怖体験のおかげで、僕の頭の中には、ずっと鬼が棲みつくことになった。人間と同じような姿形で、頭に角が生えている、それだけが違う存在。もし鬼が実在するとしたら、角には一体何の意味があるのだろう? そういうことをずっと考えていた。その造形といい力強さといい、鬼というキャラクターには、なぜか「いいなあ」と心惹かれるものがあった。 |
 | 体調は、もう最悪だった。原稿を描き出すと背中にビリビリと来る、波動というか振動が、更に強くなる。毎日必ず、下痢をする。仕事中、周囲に何か怪しいものが来ているような気がして、悪寒がする。そして寝ると必ず、怖い鬼の出てくる悪夢を見るのだ。自分の作品なのに、先の展開が全く読めない。不安で不安でたまらなかった。 |
 | こうして『手天童子』は、無事に最終回にたどりついた。いよいよ最終回かと思ったとき、何かやらなきゃいけなかった使命が一つ終わったというか、ものすごく救われた感じがした。最終回のネームは喫茶店でやっていたのだが、突然、涙がどーっとあふれてきて止まらなくなった。他のお客の目もあるし、こりゃまずいと、左腕で顔を隠しながら描いた。 |
 | 「夢」って、一体何なのだろう。睡眠中の無意識状態に、脳がいろんなシミュレーションをやっている。それが映像として形成されたものが夢だ、というのが合理的な解釈かもしれない。でも、僕には「異世界の扉を開いちゃったのかな?」としか思えないこともあるし、「親の記憶かな、それとも前世の記憶かな?」と思うときもある。 |
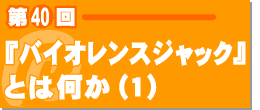 | この三十郎が見せる「格の違い」を、僕はマンガのキャラクターとして見せなければならない。そこで、「火の見櫓と人間が合体した男」として造形した。つまり、圧倒的な巨人にしたのだ。他の登場人物と常に顔の位置が違う巨人ならば、見ただけでレベルの違いがわかる。主人公がいちいち、火の見櫓に上る必要もない。動いていても大丈夫だ。 |
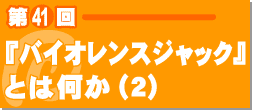 | もともと戦国時代を描くつもりで始めた作品だ。戦国武将クラスの、個性的で強いスター級のキャラクターをもっと出していかねばならない。しかし、そんなにたくさんスター級のキャラクターを作れるものでもない。いや逞馬竜のように、描けないことはないけれど、またもや生い立ちから丁寧に説明をしないといけない。それでは読者がまた飽きてしまうし、お話のパターンも似てきてしまう |
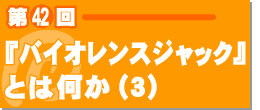 | 結局、『週刊少年マガジン』での『バイオレンスジャック』の連載は、1年ちょっとで終了することになった。「ギャグマンガの連載に切り替えましょう」と、編集部に言われたのだ。ショックだった。僕の中では、そこから先の構想が無茶苦茶広がっていたのだ。それに「石油ショック」の影響が大きかったとはいえ、不人気を理由に連載を切られたのは、初めてだった。 |
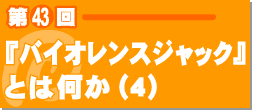 | 『バイオレンスジャック』を完結させて、あらためて思ったのだけれど、『デビルマン』を描き上げたあと、この作品に対する想い、特にあのエンディングに対する想いが、僕の中に残っていたようだ。『デビルマン』の中で、僕は一つの“世界”を、そこに住む人々もろとも消滅させた。このことに対する贖罪の意識がのしかかっていた。 |
 | 見せるモノがなくなった僕はやむなく、まだアイディアにもなっていない、イタズラ描き用のスケッチブックを見せた。すると、それをパラパラ見ていたKさんが、突然「あ! これ、これだよ!」と、ある絵を指さした。それは、僕がヒマなときに、デビルマンを女の子にしたらどうなるだろう? と、2点だけ遊んで描いたものだった。 |
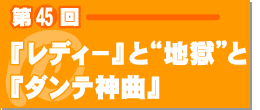 | それから20年以上たったある日、「ダンテの『神曲』をマンガ化しませんか」という話をいただいた。この作品をマンガ化しようという人は、僕のほかにいないというのだ。それもそうだな、と思った僕は、とりあえず岩波文庫版で読み返してみた。そうしたら、これがまた文語体の古い訳で読みにくく、注をいちいち参照しないと意味がわからない。 |
 | デビルマンを登場させ、同時に『ダンテ神曲』の地獄世界を取り込むことで、『デビルマンレディー』の世界は大きく広がった。そして『魔王ダンテ』の世界までも巻き込んで、単行本にして17巻という、『バイオレンスジャック』の次に長い作品になった。自分の中では、もしかしたら『デビルマン』より面白い作品かもしれない、とも思っている。 |
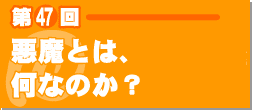 | 僕には、『デビルマンレディー』の中で描いたような事件が、実際に起き始めているように思える。人間がみんな、怒りっぽくなっているのだ。『レディー』を描いているときは、まだこういう状況になっていなかったけれど、こうなると、もはや「人間がデビルビースト化している」としか思えないときもある。 |
 | 『けっこう仮面』は、担当編集者からの注文で、エッチものというつもりで描き始めたのだけれど、同時に僕の作品の中でも、代表的な“パロディーマンガ”となった。実は僕は、大のパロディー好きなのだ。パロディーの感覚は、いつ身についたのだろうか。やはり幼い頃から落語を聴いていたせいで、斜(はす)に構えたり、物事を茶化したりするようになったのだろうか。 |
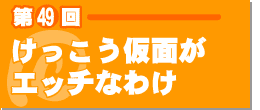 | まず、けっこう仮面が登場するシーン。実はこれは、中学生の頃に観た『ヨーロッパの夜』というイタリア映画がヒントになっている。この中に、ストリップ・ショーが出てくるのだ。舞台の袖にある緞帳の陰で、女の人がだんだん服を脱ぎながら、そろりそろりと体を露わにする。その様子に非常にドキドキしたので、この演出を使おうと思ったのだ。 |
 | このSM、それにスカトロは、大人の専売特許のようだけれど、本当はかなり「幼いエロティシズム」の発露なのかもしれない。すごく小さな頃から、恥ずかしいという感覚はある。いや、大人より強いかもしれない。それに、子供はウンコやオシッコなどの話を、非常に喜ぶ。やはり、性的な本能と繋がっているんじゃないだろうか。 |
 | 手塚治虫先生の作品の中にも、エロティシズム・ポイントがあると思う。まず、手塚先生の作品には「解剖」の場面が多い。『ブラックジャック』はもちろん手術の場面だらけだが、他の作品でもよく解剖の場面が見られる。アトムも、しょっちゅうお腹を開けられたりしている。解剖という行為には、エロティシズムのポイントが確かにあるように思う。 |
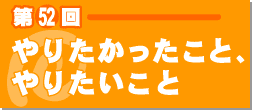 | 恋愛ものやファンタジーSFなどは、やはり少年誌の読者には、なかなか受け入れてもらえない。僕がデビューして数年たつと、少女誌では『ポーの一族』『11人いる!』の萩尾望都さん、『地球(テラ)へ…』の竹宮恵子さんが人気を集めた。僕は「こういうのが描けてうらやましいなあ」といつも思っていた。 |
 | 例えば、僕は石ノ森章太郎先生のチーフ・アシスタントをやっていたので、『サイボーグ009』をソックリな絵で描くことができる。だから、石ノ森先生が亡くなったあと、『009』の結末の絵コンテが発見されたとき、「永井豪さんなら『009』を完結させられるんじゃないですか?」と聞かれたことがあった。 |
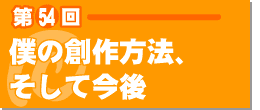 | 自分に近い年齢の読者層なら、比較的簡単だ。どんな生活をしているか、大体想像がつく。だが、低年齢層の読者の場合、考えないとわからない。読者がわからないと、的はずれな作品になってしまう。だから僕は、読者が起きてから寝るまでの一日を、頭の中で細かくシミュレーションすることにしている。 |
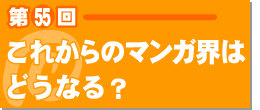 | 自分の好きな雑誌、好きな作家以外には見向きもしない、という人が増えているようなのだ。自称“マンガ好き”という人が二人、出会ったとしよう。お互いにマンガが好きだとわかって、「君は誰のマンガが好き?」と話が始まる。でも話してみたら、「へえ、そんな作家いるんだ」と、お互いに相手の好きな作家を一人も知らなかった、ということもありうる。 |
 | 取材にやってきた彼女を見て、自分で言うのは恥ずかしいけれど、「うわあ、きれいな人だなあ……」と驚いた。彼女は実に熱心に話を聞いてくれて、報知新聞のコラムでとてもいい紹介記事を書いてくれた。「きれいで、やさしくて、仕事熱心で、才能もある。あんな人がいるんだなあ」と、僕は感心した。 |
 | 僕が「電話がほしいなあ」と思っていると、突然本当に電話がかかってきた。「呼んだ?」「う、うん。連絡しようと思ってたけど……?」。こういうことが何度もあった。また、彼女といるとき、ふと他の女の人のことを思い出していたら、「あー、今こういう女の人のこと、考えていたでしょ?」と言われたことがあった。 |
 | 日本SF作家クラブは、純粋に親睦を目的とした組織で、法人でも営利団体でもない。だから逆に、メンバーが認めた人しか入れず、推薦人が2名必要ということになっている。普通は、SF作品を発表して高い評価を得た人が、メンバーの誰かが推薦されて入会に至る、という流れだ。でも僕の場合は、SF作品を描く前から知り合いになっていたし、「なんとなく気に入られて入っちゃった」という感じがしなくもない。 |
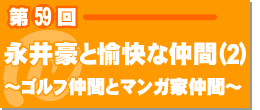 | 残念なのは、僕がマンガ家で一番仲の良かったあきおちゃん──ちばあきおさんが亡くなったことだ。彼はやさしくて他人にすごく気を遣う人なので、一緒にいて楽しく、いろんなところへ遊びに行ったり、旅行にでかけたりした。 |
 | 手塚先生には、「結婚式をすっぽかす」という、非常に困ったクセがあったのだ。どうやら、他人の幸せにジェラシーを感じるタチだったらしい。すっぽかし事件の中で、一番ものすごいケースは、故・石ノ森章太郎先生の結婚式だ。なにしろ、手塚先生は石ノ森先生の「仲人」だったのだから……。 |
 | 出演をOKしたのはいいけれど、役柄を聞いたら「佃煮評論家です」と言われた。何だろう、佃煮評論家って。しかも「衣装がないので、自前の服で出てもらえませんか」という。とにかく、低予算の映画なのだ。いろいろ考えて作務衣(さむえ)を着ていったら、ロイドは「おお! あなたはゼッタイに佃煮評論家だ!」と、よくわからないけれど大喜びしてくれた。 |
 | 僕は編集者の持っている「何か」をキャッチしてしまい、それが作品に跳ね返ってくるようなのだ。編集者の持っている、精神的なエネルギーに反応するとでもいおうか。だから、特に打ち合わせをしなくても、担当者によって、作品の性質がガラッと変わってしまう。それどころか、編集者によって、僕の中から全く別の作品が出てきてしまう。 |
 | 昔の編集者は、無茶苦茶で「この人、よく首にならないな」と思う人があちこちにいた。仕事より遊びのほうが好きで、仕事場へ来ても「締め切りはいいから、遊びに行こうよ」という人も少なからずいた。作品の打ち合わせをやるにしても、雑誌も編集部もどうでもいい、オレの好きなマンガを作るんだ、という一匹狼タイプが多かった。 |
 | また、どんなに苦労しても、売れないとダメなのだったら、思いつきで、その場の勢いでわっと描いても、結果が良ければいいんだと、開き直れるようになった。そういう意味では、作品づくりに非常に大胆になれた。一方で、効率が悪くても、自分の中でじっくり煮詰めながら描きたいときは、そうできるようになった。 |
 | だから、僕よりうんと年下の若い編集者は、遠慮せずに「こういうのを描け」と言ってほしい。「今はこういうのが当たるんだから、こういうのをやってください」と、提案してほしいのだ。明確にほしい作品を言われれば、僕だって「よっしゃ、そういうのは得意だぜい!」とか、「あ、そういうのはやったことないな。でも、やってみましょうか」ということになると思う。 |
 | ファンレターはたくさんもらったけれど、一番嬉しかったのは、こんなファンレターだ。まだデビューから間もない、『アラーくん』を連載している時のこと。ある時、僕の仕事場に、ぷっくりと膨らんだ封筒が届いた。拙い文字で宛名が書かれていて、自分の名前も住所も何も書かれてない。どうやら小さな子供の読者かららしい。 |
 | マンガ家という職業は、画家と違って原画を売るのではなく、印刷物を売ることが仕事だ。別の言い方をすれば、マスメディアを通じて作品を送り出す仕事なわけで、個人の所蔵物を描いているのではない。そのために、下描きもちゃんと時間をかけているし、アシスタントを大勢雇って、鍛えて、作品のクオリティーを最大限保てるように努力している。でも、サインを頼まれると、立ったまま下描きもしないで絵を描くことになる。 |
 | 『無頼・ザ・キッド』という僕の作品がある。人口減らしのために、銃が合法化された近未来を描いた学園SFモノだ。今だから言うけれど、実はこの作品は、最初は学園モノになる予定じゃなかった。「もしも、日本人がメイフラワー号よりも早くアメリカ大陸に渡っていたら、世界はどうなっていただろう?」という、「もしもの世界」を描きたいと思っていたのだ。 |

| 永井豪氏が生んだ史上最強のスーパーヒロイン・キューティーハニー、実写映画化! 今回の「豪氏力研究所SPECIAL」では、2004年5月29日の公開を前に、ハニーに扮する主演女優・佐藤江梨子さんとの対談が実現。“サトエリ・ハニー”の魅力、撮影中のマル秘エピソードから、作品に込められた思いまで、二人で熱く語り合っていただきました! |